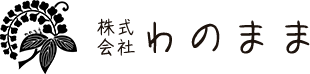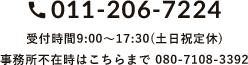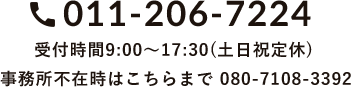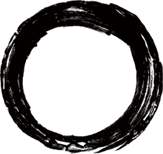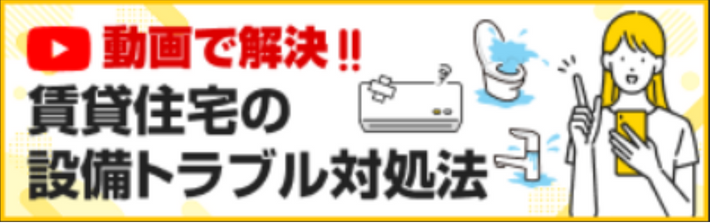親の不動産を相続したら?管理委託の方法と費用・注意点まとめ2025.09.04
親の不動産を相続すると、登記や税金といった法的な手続きに加え、建物の維持や入居者対応など、日常的な管理まで幅広い対応が必要になります。
遠方に住んでいたり仕事が忙しかったりすると、想像以上に負担が大きく感じられることもあるでしょう。
だからこそ、管理を委託する方法や費用の目安、認知症に備えた仕組みを事前に知っておくと安心です。
本記事では、親の不動産相続における管理委託の実態や備えておきたいポイントについて解説します。
親の不動産相続で管理委託を考えるタイミング

親が所有する不動産を相続する場面では、思った以上に管理の手間や負担がかかることがあります。
特に遠方に住んでいる場合や、仕事や家庭で忙しく十分に対応できない場合には、管理を委託することを前向きに考える時期かもしれません。
建物の修繕や定期的な点検、入居者への対応や家賃管理など、不動産の維持には細やかな作業が求められます。
さらに、不動産相続後は固定資産税や登記の手続きなども重なり、思わぬトラブルにつながることもあります。
親の不動産相続をスムーズに乗り越えるために、どの段階で専門の管理サービスを利用するかを意識しておくことが、今後の安心につながるでしょう。
管理委託の方法と契約の実態
不動産の管理を任せる方法には、管理会社へ依頼する形と、親族が直接対応する形があります。
空き家として残すのか、賃貸として活用するのかによって必要な管理内容は大きく変わり、契約の仕組みや実際の対応も違ってきます。
管理会社にどこまで任せられる?
不動産管理会社に依頼すると、家賃の集金や延滞時の督促といった金銭管理だけでなく、入居者募集や契約書の作成、退去時の原状回復の手配まで幅広く対応してくれます。
さらに、入居者からのクレーム処理や設備トラブルへの対応、定期的な巡回点検や建物の修繕計画の提案など、オーナーの負担を大きく減らしてくれるのが特徴です。
遠方に住んでいる方や仕事が忙しい方でも、ほとんどの実務を任せられるため安心感があります。
ただし「どこまで任せられるか」は会社や契約内容によって異なり、追加費用が発生するケースもあるため、委託範囲をしっかり確認することが大切です。
親族管理はトラブルの火種になりやすい
親族だけで不動産を管理しようとすると、思わぬ摩擦が生じることが少なくありません。
例えば、家賃収入の分配や修繕費の負担割合、空室が出たときの対応方針など、細かな判断で意見が食い違うことがあります。
管理の労力が偏ってしまうと「自分ばかり負担している」という不満が募り、兄弟姉妹や親子の関係に亀裂が入ることもあります。
さらに、不動産の法律や契約に関する知識が十分でない場合、知らずに不適切な対応をしてしまい、トラブルを拡大させる恐れもあります。
身内だからこそ率直に言い合える一方で、感情的な対立に発展しやすいため、慎重に判断する必要があります。
空き家と賃貸で異なる管理のポイント
「空き家」と「賃貸物件」では、必要となる管理の内容が大きく異なります。
空き家は“建物そのものを守る管理”が中心で、賃貸は“人や契約に関わる管理”が欠かせません。
| 管理対象 | 主な管理内容 | 注意すべきリスク |
| 空き家 | – 定期的な通風・掃除 – 庭木や雑草の手入れ – 防犯・防災対策 | ・建物の劣化が早まる ・害虫や雑草の発生 ・放火や空き巣のリスク |
| 賃貸物件 | – 家賃回収・滞納対応- 契約更新・退去時の原状回復 – 入居者からの問い合わせ対応 – 近隣トラブルの調整 | ・家賃滞納 ・入居者トラブル ・退去時の修繕負担 |
所有する不動産の状態や目的に合わせて、最適な管理体制を選ぶことが大切です。
管理費用は実際どのくらいかかる?
親の不動産を相続したあとに管理を委託すると、思った以上に費用がかかることがあります。
金額は「賃貸として貸すのか」「空き家として維持するのか」で大きく変動します。
■賃貸物件の場合
入居者がいる物件は、家賃回収や入居者対応など、日々の管理が必要になります。
- 管理料:家賃収入の 5〜10%程度
- 修繕や原状回復:数万円〜数十万円(内容による)
- 設備交換:エアコンや給湯器などは別途費用
■空き家の場合
人が住んでいない家は劣化が早いため、定期的な見回りやお手入れが中心です。
| サービス内容 | 月額の目安 |
| 定期巡回・通風 | 5,000〜10,000円 |
| 清掃・庭木の手入れ | 10,000〜20,000円 |
| 防犯確認 | 管理内容に含まれる場合あり |
どのように不動産を活用・維持するかで費用は大きく変わります。安心して任せられるよう、複数の管理会社に見積もりを依頼して比較するのがおすすめです。
認知症に備えた不動産対策

親が年齢を重ねると、判断力が緩やかに低下していく可能性もあります。
今後に備えて、不動産をどのように管理するかを事前に考えておくことは安心につながります。家族信託や成年後見制度といった仕組みを知っておくと心強いでしょう。
認知症でも売却できる「家族信託」
家族信託は、親が認知症になった後でも不動産の売却や管理を進められる仕組みです。
親が元気なうちに信頼できる家族と契約を結び、財産の管理や処分を任せておくことで、介護費用や施設入居費用にあてるために不動産を売却することも可能です。
成年後見制度と比べて柔軟に条件を決められるのが特徴で、「売却益を孫の教育資金にまわす」といった希望も取り入れられます。
また、信託財産は受託者の財産と分けて扱うため、破産や相続の影響を受けにくい点も安心です。
ただし、契約書の作成には専門的な知識が欠かせないことから、家族間での信頼関係が前提となります。
財産を裁判所が守る「成年後見制度」
成年後見制度は、判断力が低下した親の財産を家庭裁判所の監督のもとで守る制度です。
裁判所が選んだ後見人が、預貯金や不動産などを適切に管理し、不正やトラブルを防ぎます。
不動産を売却する場合は、介護費用が必要といった合理的な理由を示し、裁判所の許可を得ることが求められます。
そのため、本人に不利益な売却が行われにくく、安全性の高い仕組みです。
ただし、家族信託のように自由度は高くないため、活用方法に制限がある点は注意が必要です。
また、後見人の活動には継続的に裁判所のチェックが入るため、手続きや費用の負担が続くことも理解しておきたい点です。
相続で欠かせない手続きとお金の準備
親の不動産を受け継ぐときには、名義変更の相続登記や税金の支払いなど、避けられない手続きがあります。
司法書士や税理士といった専門家の力を借りる場面も出てくるため、事前に流れを把握しておくと安心です。
相続登記を怠ると不動産は動かせない
親の不動産を相続した場合、まず必要になるのが「相続登記」です。
名義を親から相続人へ正式に移す手続きで、相続登記を行わなければ不動産を売却したり、賃貸に出して管理会社へ委託したりすることが出来ません。
相続登記を放置していると、名義が被相続人のまま残ってしまい、金融機関や不動産会社の手続きが一切進まなくなります。
相続人が複数いる場合、誰がその不動産を管理するのか不明確になり、売却や利用の話し合いがまとまらず、トラブルの火種になることも少なくありません。
2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由が無いまま手続きを怠ると過料の対象になります。
相続登記は書類も多く複雑なため、司法書士に依頼して早めに進めるようにしましょう。
相続税や固定資産税にどう備える?
親の不動産を引き継ぐと、相続税だけでなく毎年の固定資産税も負担することになります。
相続税は財産の評価額や相続人の人数によって大きく変わるため、「いくらかかるのか」が分かりづらい点が特徴です。
特に現金が少なく不動産が多い相続では、納税資金をどう準備するかが大きな課題となります。
不動産を売却して資金をつくるケースも多く見られますが、手続きには時間がかかるため、早めに見通しを立てておくことが大切です。
また、相続後は固定資産税を毎年払い続ける必要があり、空き家でも負担は免れません。
放置された空き家は「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇が外れて税額が上がることもあります。
税に関するリスクを避けるためには、税理士に相談して早い段階で相続税の試算や納税シミュレーションを行い、安心できる資金計画を立てておくと良いでしょう。
司法書士や税理士に依頼するべき場面とは
相続に関する手続きは、思った以上に複雑で時間もかかります。
戸籍の収集や相続登記といった法的な部分は司法書士が専門で、名義変更の流れをスムーズに進めてくれます。
一方、相続税や固定資産税の申告は税理士の分野で、財産評価や節税のアドバイスも含めてサポートしてくれます。
特に不動産を複数所有していたり、相続人が多く話し合いがまとまりにくい場合には、専門家が間に入ることで不要な争いを防げることもあります。
さらに、将来的に管理委託や売却を考えているなら、専門家と早めに連携しておくことで安心して進められます。
費用は数十万円単位でかかる場合もありますが、その分トラブルを避け、長期的には時間と労力を大きく節約することにつながるでしょう。
まとめ
親の不動産を相続すると、登記や税金の手続きに加え、建物の維持や入居者への対応など、幅広い作業が必要になります。
遠方に暮らしていたり日々の仕事で手一杯だったりすると、自分だけで抱えるのは大変に感じることもあるでしょう。
そうしたときに管理会社へ委託すれば、大きく負担を減らすことが出来ます。
また、親が将来認知症になった場合を考えて、家族信託や成年後見制度といった制度を理解しておくことが重要です。
相続登記の義務化や固定資産税の負担といった面にも向き合いながら、司法書士や税理士などに相談することも、長期的な安心材料となるでしょう。